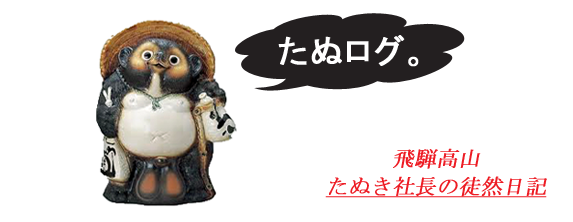やっぱりお宝でした!
2011年07月27日
先週、「仙人台屋台蔵」のお引越しの際、衣装箱の中から見つかった大きな旗ですが、
明治22年9月に「日下部東作」という方が書いたと記されていました。
「日下部東作」さんとは?・・・・・・・・・調べました。実はなかなかの人物だったのです。
本名 日下部東作、雅号 日下部鳴鶴(めいかく) 天保9年(1838年)滋賀県生まれ。
彦根藩士で、明治維新後は太政官内閣大書記官を務め、信任篤かった大久保利通が
暗殺されたのち、官位を辞して書道に専念しました。力強い筆跡が特徴で、和式だった
日本の書法を唐式に作り変えた、「近代書道の確立者」で 「明治の三筆」と呼ばれる
有名な書家が書かれた貴重なものでした。

この旗は、櫻山八幡宮の祭礼の時に「辻旗」として、三之町のどこかに立てられていたと
想像できます。長さ9mの「大旗」ですから竿建ても大変だったんでしょうね。^^

八幡宮との関係を瀬木学芸員に尋ねたところ、櫻山日光館に「日下部鳴鶴」の掛け軸が
展示してありました。「飛騨八幡宮」と書かれた書体には、見る人が「これ間違ってる」と
指摘されるように「幡」のノの字や「宮」のノの字がありません。 これこそ鳴鶴の書法で
「大旗」の幡の字もまったく同じです。

この掛け軸の「飛騨八幡宮」の書体で、祭礼の先頭をいく「社名旗」は代々作られて
います。普段は屋台会館のなかに展示してある旗で見ることができます。(下右)

どんな経緯で高山に来て、八幡宮との関わりなどはわかっていませんが、今回の発見で
明治22年の9月には、確実に高山の町にみえたという事がわかりますよね。^^
江戸時代以降、特に明治になると「高山」には、多くの著名な画家や書家が作品を残して
おられます。当時から「高山」はアカデミックな町だったんでしょうか?。木材・酒造などの
地場産業で潤った当時の豪商の家に長期逗留して、作品を残したのでしょうか?
そんなこんな思い浮かべると、この町のご先祖様たちは「たいしたもんやったな」と改めて
感心感激です。!
ということで、この旗は我が屋台蔵から八幡宮へ移し、永く保存されることになりました。^^
明治22年9月に「日下部東作」という方が書いたと記されていました。
「日下部東作」さんとは?・・・・・・・・・調べました。実はなかなかの人物だったのです。
本名 日下部東作、雅号 日下部鳴鶴(めいかく) 天保9年(1838年)滋賀県生まれ。
彦根藩士で、明治維新後は太政官内閣大書記官を務め、信任篤かった大久保利通が
暗殺されたのち、官位を辞して書道に専念しました。力強い筆跡が特徴で、和式だった
日本の書法を唐式に作り変えた、「近代書道の確立者」で 「明治の三筆」と呼ばれる
有名な書家が書かれた貴重なものでした。

この旗は、櫻山八幡宮の祭礼の時に「辻旗」として、三之町のどこかに立てられていたと
想像できます。長さ9mの「大旗」ですから竿建ても大変だったんでしょうね。^^

八幡宮との関係を瀬木学芸員に尋ねたところ、櫻山日光館に「日下部鳴鶴」の掛け軸が
展示してありました。「飛騨八幡宮」と書かれた書体には、見る人が「これ間違ってる」と
指摘されるように「幡」のノの字や「宮」のノの字がありません。 これこそ鳴鶴の書法で
「大旗」の幡の字もまったく同じです。

この掛け軸の「飛騨八幡宮」の書体で、祭礼の先頭をいく「社名旗」は代々作られて
います。普段は屋台会館のなかに展示してある旗で見ることができます。(下右)

どんな経緯で高山に来て、八幡宮との関わりなどはわかっていませんが、今回の発見で
明治22年の9月には、確実に高山の町にみえたという事がわかりますよね。^^
江戸時代以降、特に明治になると「高山」には、多くの著名な画家や書家が作品を残して
おられます。当時から「高山」はアカデミックな町だったんでしょうか?。木材・酒造などの
地場産業で潤った当時の豪商の家に長期逗留して、作品を残したのでしょうか?
そんなこんな思い浮かべると、この町のご先祖様たちは「たいしたもんやったな」と改めて
感心感激です。!
ということで、この旗は我が屋台蔵から八幡宮へ移し、永く保存されることになりました。^^
スポンサーリンク
Posted by てらちゃん at 12:39│Comments(0)