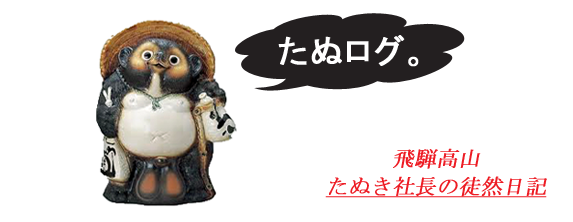「開運なんでも鑑定団」で・・!
2012年03月28日
今朝もまた雪! このところ冬春のオセロゲームみたい^^ 早く春勝て(^^)

東山寺院「大雄寺」本堂もまた真っ白!
昨晩の「開運なんでも鑑定団!」を見てたら、「45年間売らなかった道具」がでてきました。
広島県の金物屋さん東光さんの所持品の「墨壷」2点!


ケヤキ(欅)で彫られた大正時代の匠、「木村伊三郎」さんの作られたもので広島県の
貿易博覧会に大正12年に出展されたそうです。
墨壷とは・・・・簡単に言えば木材に直線の墨を打つ道具です。
同様の道具は、人類の歴史の中では古代エジプトでも使用されていました。日本では
「奈良時代」のものが「正倉院」に現存するので、それ以前から使われていた可能性が
あります。

昔の神社造営の絵巻物(春日大社霊験記)には匠の「三種の神器」である、ちょうな(釿)・
さしがね(差金)とすみつぼ(墨壷)を使って作業しているところが残っています。

「忘れ物の墨壷」として明治時代に見つかった「東大寺南大門」の天井裏にあった墨壷!

奈良時代に造営に携わった匠の棟梁が、自分の一世一代の仕事の証として天井裏に
残したのではと言われています。「南大門」へ行って天井・梁を見上げると時空を超えて
棟梁の姿が目に浮かぶような気がします。(^^)
また「日光東照宮」が造営された時の「三種の神器」は、国宝に指定され大切に保存
されています。

さて広島県の金物屋さんの「墨壷」2点、いくらで鑑定されたと思いますか????^^
なんと・・・・・・・・・・・200万円!
ちょっと状態が悪くてこの値段ですから、漆などちゃんとしてたらもっと高くなったようです!
飛騨の匠の墨壷としてはこの地方独特の形の「墨壷」があります。^^
「一文字壷」といわれる形です。

筆で一の文字を書いたような姿なので「一文字壷」と呼ばれています。

写真の墨壷は、明治時代の飛騨の匠で川原町の「直井貞次郎」のものです。石浦の
「速入寺」や清見町小鳥のお寺の造営に携わった匠だったそうです。
昭和30年頃私の父が直井さんからいただいたものと聞いています。
いい仕事はいい道具から・・・・飛騨の匠の歴史はこんなところにも(^^)

東山寺院「大雄寺」本堂もまた真っ白!
昨晩の「開運なんでも鑑定団!」を見てたら、「45年間売らなかった道具」がでてきました。
広島県の金物屋さん東光さんの所持品の「墨壷」2点!


ケヤキ(欅)で彫られた大正時代の匠、「木村伊三郎」さんの作られたもので広島県の
貿易博覧会に大正12年に出展されたそうです。
墨壷とは・・・・簡単に言えば木材に直線の墨を打つ道具です。
同様の道具は、人類の歴史の中では古代エジプトでも使用されていました。日本では
「奈良時代」のものが「正倉院」に現存するので、それ以前から使われていた可能性が
あります。

昔の神社造営の絵巻物(春日大社霊験記)には匠の「三種の神器」である、ちょうな(釿)・
さしがね(差金)とすみつぼ(墨壷)を使って作業しているところが残っています。

「忘れ物の墨壷」として明治時代に見つかった「東大寺南大門」の天井裏にあった墨壷!

奈良時代に造営に携わった匠の棟梁が、自分の一世一代の仕事の証として天井裏に
残したのではと言われています。「南大門」へ行って天井・梁を見上げると時空を超えて
棟梁の姿が目に浮かぶような気がします。(^^)
また「日光東照宮」が造営された時の「三種の神器」は、国宝に指定され大切に保存
されています。

さて広島県の金物屋さんの「墨壷」2点、いくらで鑑定されたと思いますか????^^
なんと・・・・・・・・・・・200万円!
ちょっと状態が悪くてこの値段ですから、漆などちゃんとしてたらもっと高くなったようです!
飛騨の匠の墨壷としてはこの地方独特の形の「墨壷」があります。^^
「一文字壷」といわれる形です。

筆で一の文字を書いたような姿なので「一文字壷」と呼ばれています。

写真の墨壷は、明治時代の飛騨の匠で川原町の「直井貞次郎」のものです。石浦の
「速入寺」や清見町小鳥のお寺の造営に携わった匠だったそうです。
昭和30年頃私の父が直井さんからいただいたものと聞いています。
いい仕事はいい道具から・・・・飛騨の匠の歴史はこんなところにも(^^)
スポンサーリンク
Posted by てらちゃん at 11:21│Comments(0)